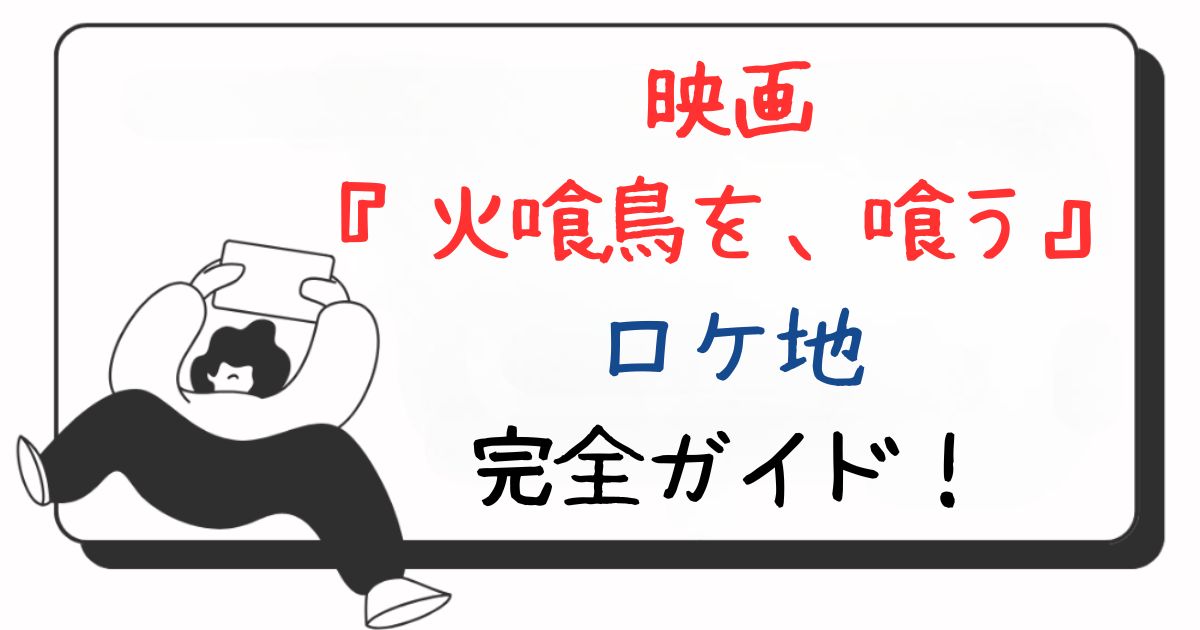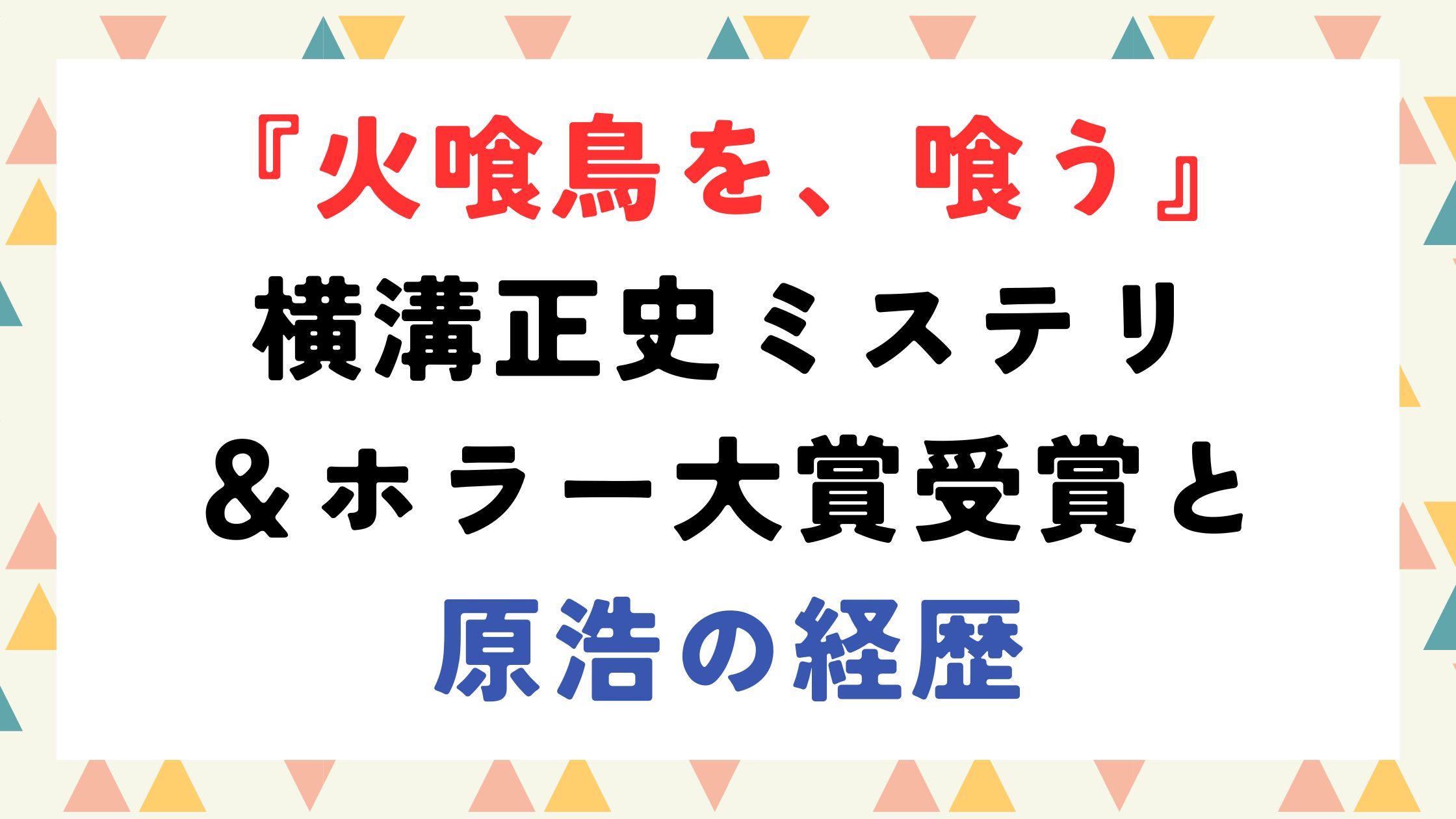映画化された『火喰鳥を、喰う』は、ただの映像作品ではなく、文学賞で高く評価された小説が原作になっています。
本作は第30回横溝正史ミステリ&ホラー大賞で大賞を受賞した原浩さんによる作品です。
この記事では、
『火喰鳥を、喰う』の原作!横溝正史ミステリ&ホラー大賞受賞と原浩の経歴
と題して、この小説がどのように評価されたのか、文学賞の意味、そして原作者である原浩さんの経歴や作家としての歩みについて詳しく解説します。
映画をより深く味わいたい方に向けた内容です。
 どき子
どき子最後までごゆっくりお読みください!
「火喰鳥を、喰う」と横溝正史ミステリ&ホラー大賞
まずは、原作小説『火喰鳥を、喰う』がどのようにして文学賞に選ばれたのかを見ていきましょう。
大賞受賞の意義
『火喰鳥を、喰う』は、第30回横溝正史ミステリ&ホラー大賞において見事大賞を受賞しました。
この賞は、推理小説の巨匠・横溝正史の名を冠し、ミステリとホラーというジャンルで新しい才能を発掘するために設立されたものです。
大賞作品は新人作家にとって大きな飛躍のチャンスとなり、受賞と同時に商業出版が決定されるのが特徴です。
つまり『火喰鳥を、喰う』は、応募段階から高い完成度を評価され、選考委員の厳しい審査を突破した作品なのです。
「死者の日記」から始まったのは、
— Koshi Mizukami 水上恒司 &STAFF【公式】 (@koshi_mizukami) March 5, 2025
“事件”か、あるいは“怪異”か。
------------
第40回横溝正史ミステリ&ホラー大賞受賞作
「火喰鳥を、喰う」を実写映画化決定!#水上恒司 は主人公・久喜雄司役にて
主演を務めさせていただきます。
久喜雄司の妻・久喜夕里子役には#山下美月… pic.twitter.com/A0vY806OaZ
選考委員の評価ポイント
選考委員たちは『火喰鳥を、喰う』の物語構成と筆致の巧みさを高く評価しました。
特に注目されたのは、伝承と現代社会を融合させる大胆な発想力と、読者を物語に引き込む緻密な描写力です。
ホラー的恐怖とミステリ的謎解きが見事に組み合わさり、最後まで緊張感が持続する構成は、従来のホラー小説を超えた完成度と評価されました。
受賞は決して偶然ではなく、作家としての力量が認められた結果だったのです。
 どき子
どき子大賞の評価にふさわしい完成度が、観る人・読む人を物語の深みへと引き込みます。
「火喰鳥を、喰う」原作小説の魅力
続いて、文学賞を勝ち取った原作小説『火喰鳥を、喰う』そのものの魅力を見ていきましょう。
原作に描かれる世界観
物語の舞台は山間の閉ざされた集落です。
そこには「火喰鳥」という不気味な存在の伝承が残され、人々はその恐怖に支配されています。
作者の原浩さんは、この伝承を単なる怪談ではなく、人間の罪や共同体の闇を映し出す装置として描きました。
恐怖の対象を外に求める村人たちの心理が巧みに表現されており、読者は登場人物と同じように「火喰鳥」の正体を追い求めながら物語に没入していきます。
📣『火喰鳥を、喰う』実写映画化決定‼️
— 角川ホラー文庫編集部 (@KadokawaHorror) March 5, 2025
原浩さんのデビュー作である
第40回横溝正史ミステリ&ホラー大賞
統合後初の〈大賞〉受賞作
『火喰鳥を、喰う』の
実写映画化が発表されました🎉
素敵なキャスト、素晴らしい監督の手で
どんな映像になるのか、
10月の公開日まで楽しみにお待ちください✨🎥 pic.twitter.com/Rp8neGsrDx
ミステリとホラーの融合
本作の大きな魅力は、ホラー的恐怖にミステリ的仕掛けを組み合わせた点にあります。
序盤は不穏な空気と怪異の予兆が描かれ、中盤では事件の真相を探る謎解きが展開されます。
そして後半には恐怖と謎が一気に収束し、読者を圧倒するクライマックスが訪れます。
この構成は、ホラーの感覚的な怖さとミステリの知的な面白さを両立させており、受賞理由のひとつにもなりました。
読者からの反響
出版後の反響も大きく、ホラー読者はもちろん、普段ホラーをあまり読まないミステリファンからも高い支持を集めました。
口コミやレビューでは「最後まで緊張感が続く」「映像的な描写が映画向き」といった声が多く見られ、映画化に至る下地となったことも頷けます。
まさに小説としての成功と映像化の可能性を同時に証明した作品だったのです。
 どき子
どき子原作が放つ独特の世界観は、映画でもきっと大きな魅力となるはずです。
原浩の経歴と作家としての歩み
では、受賞作を世に送り出した原浩さんとはどのような人物なのでしょうか。
ここでは経歴や作家としての特徴を解説します。
作家デビューのきっかけ
原浩さんは、かねてより小説執筆を続けていた作家志望の人物であり、『火喰鳥を、喰う』で新人賞に応募したことがきっかけで大きなチャンスをつかみました。
受賞によって一気に注目を集め、デビュー作にして映画化という快挙を成し遂げた点は、文学界でも稀有な例といえます。
経歴に見る作風の源泉
原浩さんの作風は、地方の風土や人々の心に潜む闇を掘り下げることに特徴があります。
学生時代から怪談や伝承に関心を持ち、それを小説の題材に取り入れることが多かったと伝えられています。
特に『火喰鳥を、喰う』では、その関心が結実し、伝承をテーマに人間ドラマを描く独自の作風が確立されました。
今後もホラーやミステリのジャンルで活躍が期待されています。
原浩さん『火喰鳥を、喰う』
— ミント (@mint130408) February 28, 2021
好きな世界観で一気読み。欲を言えばもう少し登場人物たちに厚みを持たせて欲しかったが(特に女性陣)むせ返るような夏の気配とゾワっと背筋を撫でるような冷たい気配にページをめくる手が止められなかった。デビュー作とのことで次作以降も期待したい。#読了 #読書 pic.twitter.com/FtyIrFiynn
映画化による新たな展開
受賞作の映画化は、原浩さんにとってさらなる飛躍の契機となりました。
小説として評価されるだけでなく、映像作品として多くの観客に届くことで、作家としての知名度が一気に高まったのです。
映像化によって原作のテーマや魅力が広く伝わり、今後の創作活動への期待も高まっています。
 どき子
どき子デビュー作から映画化という快挙を果たした原浩さん、これからの作品にも注目が集まりそうです。
「火喰鳥を、喰う」横溝正史ミステリ&ホラー大賞まとめ
『火喰鳥を、喰う』は、第30回横溝正史ミステリ&ホラー大賞で大賞を受賞したことで、その完成度と独自性を証明しました。
原作者の原浩さんは、この受賞をきっかけに作家デビューを果たし、映画化という大きな成果へとつなげました。
作品はミステリとホラーを融合させた独自の構成で読者を魅了し、原作者の経歴や作風も大きな注目を集めています。
文学賞受賞作として、そして映画化作品として、『火喰鳥を、喰う』は今後も長く語り継がれるでしょう。
 どき子
どき子ミステリ好きもホラー好きも楽しめる『火喰鳥を、喰う』、ぜひチェックしてみてください。